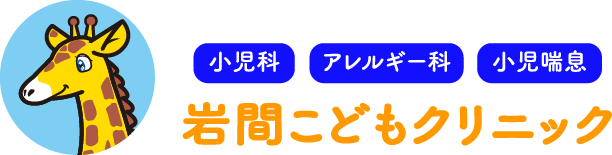HPVワクチンは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染を予防するためのワクチンです。このウイルスは子宮頸がんや性器いぼなどの原因となることが知られています。HPVワクチンは、これらの病気の発症リスクを大幅に下げることができる有効な予防手段です。
HPVワクチンの導入によって、世界各地で子宮頸がんの発症率が顕著に低下しています。ワクチン接種は、特に性行為を始める前の若年層に対して推奨されています。ワクチンは体内に抗体を作ることで、HPVが体に侵入するのを防ぎ、長期的な健康を守る役割を果たします。
日本でも、子宮頸がんの予防に対する関心が高まっており、HPVワクチンの接種が定期接種として位置づけられています。適切なタイミングで接種することで、将来的な健康リスクを軽減することが期待されています。
HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス)
Human papillomavirus vaccine